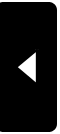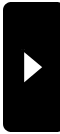2017年03月03日
ひな祭り
「子供は宝」。どの子もスクスクと元気に育って欲しい。小さな子供をみると、いつもそんな気持ちになる。少子化がすすむ日本。子育て環境は厳しいが、未来を背負う子供達。安心して子育てができる社会に、と思う。

(写真の雛人形は、奈良一刀彫人形師 染川宗進の作品)
(写真の雛人形は、奈良一刀彫人形師 染川宗進の作品)
2017年02月27日
五色南天
庭の五色南天(別名オタフクナンテン)。あまり目立たない草木。垣根などにつかわれる低木で、それほど気に留めていなかったが、今年は綺麗に紅葉しているので、その姿が消える前にご披露。メギ科ナンテン属の草木。花がつかないのに花言葉があるのにびっくり。ナンテンの花言葉と同じとか。「私の愛は増すばかり」「機知に富む」「福をなす」「よい家庭」など。「難が転ずる」という縁起のよい魔除けの花言葉。

2017年02月22日
市長の変節
大沼明穂市長は沼津駅付近鉄道高架事業について、昨年の市長選を通じ、「見直し、検証する」と表明していた。そして、当選後の市議会11月定例会における所信表明で「専門家による検証チームを立ち上げる」としていた。
それが一転、「世界一元気な沼津には必要」だとして、就任わずか3カ月で「鉄道高架推進」となった。約束した検証もしないで推進とは、市民も馬鹿にされたものだ。
そもそも「世界一」が何を目指して世界一かも分からないが、それよりも何よりも、「市長になるためには嘘をついてもいい」としか思えない結末は、子ども達の教育上も良くない。このことは鉄道高架の推進、見直しを別にしても、そうは言えないだろうか。
ただ、私にとって市長の変節は、「やはり」というのが実感である。
私は、市長選の告示を前にした昨年10月22日付の本紙に「沼津市長選の争点は何か」というタイトルで投稿し、立候補を予定していた大沼氏の高架事業に対する曖昧な態度を指摘して、リーダーとは、そういうことであってはいけないと暗に警鐘を鳴らした。
しかし、その曖昧さが市民の期待につながったのか、当選を果たしたが、市民の期待に応えられないのでは、「市民ファースト」ではなく、「自分ファースト」と言わざるを得ない。二枚舌、八方美人は結局、自分自身を追い込むことになる。
今となってはもう遅いが、鉄道高架をめぐる市長の対応は、市民の期待を裏切ったのみならず、政治に対する市民の不信を募らせたということで、その責任は大きい。
市長は、組織票もなく、なぜ4万3千人もの票を獲得し当選できたのか、この結果に真摯に向き合うことが必要だ。
このままでは市民の代表とは言えない。そして、自らの身は自ら処していかなければ後世まで「ふがいない市長」と言われるだろう。
カルロス・ゴーンは自著の『経営論』で、リーダーとは「自分一人でも『ノー』と言える人こそリーダーである」と論じている。
最後に市議会である。大沼市長の変節に対して市議会の空気は、当初の警戒感から安堵感さえ漂っている感じだ。
私は問いたい。嘘をつく人が、このまちのリーダーであっていいのかと。そういう政治がはびこってきたことが、今の沼津の現状を招いたのではないだろうか。
市民の代表でもある一方の市議会が、嘘をつくリーダーを仮にも認めるようであったら、市議会自体が、姿勢、資質が問われることになる。市議会の良識ある対応を望みたい。
(平成29年2月22日沼津朝日新聞 中山康之投稿文転載)

(庭の椿)
それが一転、「世界一元気な沼津には必要」だとして、就任わずか3カ月で「鉄道高架推進」となった。約束した検証もしないで推進とは、市民も馬鹿にされたものだ。
そもそも「世界一」が何を目指して世界一かも分からないが、それよりも何よりも、「市長になるためには嘘をついてもいい」としか思えない結末は、子ども達の教育上も良くない。このことは鉄道高架の推進、見直しを別にしても、そうは言えないだろうか。
ただ、私にとって市長の変節は、「やはり」というのが実感である。
私は、市長選の告示を前にした昨年10月22日付の本紙に「沼津市長選の争点は何か」というタイトルで投稿し、立候補を予定していた大沼氏の高架事業に対する曖昧な態度を指摘して、リーダーとは、そういうことであってはいけないと暗に警鐘を鳴らした。
しかし、その曖昧さが市民の期待につながったのか、当選を果たしたが、市民の期待に応えられないのでは、「市民ファースト」ではなく、「自分ファースト」と言わざるを得ない。二枚舌、八方美人は結局、自分自身を追い込むことになる。
今となってはもう遅いが、鉄道高架をめぐる市長の対応は、市民の期待を裏切ったのみならず、政治に対する市民の不信を募らせたということで、その責任は大きい。
市長は、組織票もなく、なぜ4万3千人もの票を獲得し当選できたのか、この結果に真摯に向き合うことが必要だ。
このままでは市民の代表とは言えない。そして、自らの身は自ら処していかなければ後世まで「ふがいない市長」と言われるだろう。
カルロス・ゴーンは自著の『経営論』で、リーダーとは「自分一人でも『ノー』と言える人こそリーダーである」と論じている。
最後に市議会である。大沼市長の変節に対して市議会の空気は、当初の警戒感から安堵感さえ漂っている感じだ。
私は問いたい。嘘をつく人が、このまちのリーダーであっていいのかと。そういう政治がはびこってきたことが、今の沼津の現状を招いたのではないだろうか。
市民の代表でもある一方の市議会が、嘘をつくリーダーを仮にも認めるようであったら、市議会自体が、姿勢、資質が問われることになる。市議会の良識ある対応を望みたい。
(平成29年2月22日沼津朝日新聞 中山康之投稿文転載)

(庭の椿)
2017年02月19日
季節は春、すぐそこ。沼津は冬、ずっと。
季節は、庭の草花に春のきざし。クリスマスローズが紫色の花つぼみで、まさに咲かんと。
しかし、沼津のまちは、いい加減な(公約を守れない)市長の下で市政が混乱・混迷。やる気もないことを公約にし、騙したのは市長だが、選んだのは市民。政治は益々遠く、市民は背を向ける。
悲しいかな、それがまた跳ね返って、帰ってくるのも市民。このまちの長い冬が続く。

しかし、沼津のまちは、いい加減な(公約を守れない)市長の下で市政が混乱・混迷。やる気もないことを公約にし、騙したのは市長だが、選んだのは市民。政治は益々遠く、市民は背を向ける。
悲しいかな、それがまた跳ね返って、帰ってくるのも市民。このまちの長い冬が続く。
2017年02月16日
沼津の混迷
沼津市長、就任2カ月で小脳出血で入院。3週間の入院後、出て来ればすぐに「鉄道高架推進」と表明。健康のことも心配だが、この変節、一体どうなっているのか。
市長は選挙前、沼津駅鉄道高架に関して「賛成でも反対でもない」と、そもそも曖昧な態度だった。しかし、「見直し、検証する」と市民に約束したはず。
その市長の言葉に、どれだけの市民が期待したか。それを裏切るように、検証もしないで、「高架推進」と。何を血迷ったのか。はじめから市民ファーストでなく自分ファーストだったのか。市民は怒るだろう。政治に対する不信を与えたのは市長自らだ。責任を自覚してもらいたい。
 (千本浜からの富士山)
(千本浜からの富士山)
市長は選挙前、沼津駅鉄道高架に関して「賛成でも反対でもない」と、そもそも曖昧な態度だった。しかし、「見直し、検証する」と市民に約束したはず。
その市長の言葉に、どれだけの市民が期待したか。それを裏切るように、検証もしないで、「高架推進」と。何を血迷ったのか。はじめから市民ファーストでなく自分ファーストだったのか。市民は怒るだろう。政治に対する不信を与えたのは市長自らだ。責任を自覚してもらいたい。

2017年02月03日
春を待つ
寒いといっそう春が恋しい。春を恋しく思うのは人だけでなく花木もそのようだ。寒々しい庭の花木も春を待つように花の蕾(つぼみ)を膨らます。ツバキ、セイヨウヒイラギ、クリスマスローズ、と。このほかスイセンやシランもにょきにょきと、とんがり帽子のように芽を出す。すぐそこの春の匂いを嗅ぎ分けるように。今日は節分。明日は立春。






2017年01月23日
2017年01月06日
地方創生と物流問題を考える
日本の元気は地方から。沼津のまちの創生がどうなのか、との検証するページをフェイスブックでつくりました。
「地方創生と物流問題を考える」
https://www.facebook.com/nipponikiiki/

「地方創生と物流問題を考える」
https://www.facebook.com/nipponikiiki/

2017年01月01日
2016年12月24日
クリスマスに寄せて
今年もあと僅か。世の中、いろいろなことがあった1年。でも街には何事もなかったようにイルミネーションが輝く。
先日、清水寺の貫主が揮毫し、発表された今年の世相を現す漢字は「金」。私には「金」というものに縁がない。ただ「金(カネ)」にまつわる不正や腐敗の話題には関心がある。そこに社会の悪と不条理が潜んでいるからだ。そういうことを許す社会であってはならない。
そのことは別に、齢を重ねると毎年の自分を現す一字はいつも変わらない。その一字は「康」である。身体が丈夫である「健康」と、事故や苦がなく「やすらか」であることを示す一字。広く社会のすべても「康」であってほしい。
クリスマス。子供や孫らと過ごす。いつまでもこの子らが健やかに、やすらかに、そんな社会に、と願い。メリークリスマス。

先日、清水寺の貫主が揮毫し、発表された今年の世相を現す漢字は「金」。私には「金」というものに縁がない。ただ「金(カネ)」にまつわる不正や腐敗の話題には関心がある。そこに社会の悪と不条理が潜んでいるからだ。そういうことを許す社会であってはならない。
そのことは別に、齢を重ねると毎年の自分を現す一字はいつも変わらない。その一字は「康」である。身体が丈夫である「健康」と、事故や苦がなく「やすらか」であることを示す一字。広く社会のすべても「康」であってほしい。
クリスマス。子供や孫らと過ごす。いつまでもこの子らが健やかに、やすらかに、そんな社会に、と願い。メリークリスマス。
2016年10月02日
沼津市長選の争点は何か
沼津市長選が間もなくである。現在まで出馬表明した候補者は現職含め2人。それぞれの候補者の出馬理由は新聞報道などで見たが、争点が何か、よくわからない。
現職候補者は沼津駅鉄道高架の推進を唱え、それが争点と位置付ける。しかし前回の市長選では「高架は争点でない」と言っていたはずである。それが今回は「争点だ」と言いだしたのが不思議である。一方の候補者は、鉄道高架が争点でないと言い、だからといって何が争点か示していない。
先日(9月4日)、原地区センターで、一方の候補者が「市民と語る会」を開くというので行ってみた。ここで、その候補者は「鉄道高架は賛成でも反対でもない」としたうえで、市長に就任したら財政を見て考える、と説明。至極もっともなように聞こえる。
しかし、この問題は昨日今日始まったことでない。出馬にあたっては、事前にもっと勉強し、自らの考えをしっかり主張してもらいたい。それがなく高架の是非に触れないでは、有権者からすれば「白紙委任しろ」、と言われているのと同じである。
候補者のチラシには一応見直しと触れているが、この一言で理解しろというのは、少し乱暴すぎるのでないだろうか。さらにこの候補者は「高架は争点でない」としているが、それでは現職と同じ高架推進の立場かと、うがった見方になってしまう。
川勝平太静岡県知事は就任時、鉄道高架は見直すとして、有識者会議やPI委員会など開き、点検作業を行ってきた。私はそのほとんどを傍聴してきたが、内容は「高架ありき」で、見直すべきという様々な意見には耳をかさなかった。結果、川勝知事は見直しどころか推進とした。静岡県では「見直し」という言葉がいかに軽いものかがわかる。
「白紙委任」するということは、有権者の意図しない判断になる可能性がある。それはどちらの立場(高架推進あるいは見直し)に立ったとしても、どちらかが意図しない結果になる。
また高架の是非が有権者の投票行動のすべてでないにしても、現状このことが沼津市政のリーダー選びに大きな要素となる。なぜならばこの問題がこれからのまちづくりや市民生活に大きな影響を与えるからだ。
4日の「語る会」を聴いたなかでは、このままの市長選では盛り上がらないのでないかと。何しろ具体的な施策ひとつも聴けなかったからだ。それはそうだろう。鉄道高架の是非を抜きにして沼津のビジョンや施策は語れない。
翻って、ついこの間行われた東京都知事選。当選した小池百合子知事はその選挙戦で、オリンピック施設の再検討、待機児童問題解消、行財政改革、韓国学校への都有地貸出取り止め、市場移転の点検、無電柱化、知事給与削減など、具体的な施策をいろいろと打ち出し、また議会との対決も辞さずと、その態度を鮮明に打ち出していた。その都知事選を目の当たりにすると、沼津市の市長選に寂しさを感じる。
候補者の人たちへ望みたい。鉄道高架問題の現実をスルーしては、沼津の将来が見えない。それ故、その是非のうえにたって、まちのビジョンを描き、その具体的な施策を示し、堂々と論戦を張っていただきたい。

現職候補者は沼津駅鉄道高架の推進を唱え、それが争点と位置付ける。しかし前回の市長選では「高架は争点でない」と言っていたはずである。それが今回は「争点だ」と言いだしたのが不思議である。一方の候補者は、鉄道高架が争点でないと言い、だからといって何が争点か示していない。
先日(9月4日)、原地区センターで、一方の候補者が「市民と語る会」を開くというので行ってみた。ここで、その候補者は「鉄道高架は賛成でも反対でもない」としたうえで、市長に就任したら財政を見て考える、と説明。至極もっともなように聞こえる。
しかし、この問題は昨日今日始まったことでない。出馬にあたっては、事前にもっと勉強し、自らの考えをしっかり主張してもらいたい。それがなく高架の是非に触れないでは、有権者からすれば「白紙委任しろ」、と言われているのと同じである。
候補者のチラシには一応見直しと触れているが、この一言で理解しろというのは、少し乱暴すぎるのでないだろうか。さらにこの候補者は「高架は争点でない」としているが、それでは現職と同じ高架推進の立場かと、うがった見方になってしまう。
川勝平太静岡県知事は就任時、鉄道高架は見直すとして、有識者会議やPI委員会など開き、点検作業を行ってきた。私はそのほとんどを傍聴してきたが、内容は「高架ありき」で、見直すべきという様々な意見には耳をかさなかった。結果、川勝知事は見直しどころか推進とした。静岡県では「見直し」という言葉がいかに軽いものかがわかる。
「白紙委任」するということは、有権者の意図しない判断になる可能性がある。それはどちらの立場(高架推進あるいは見直し)に立ったとしても、どちらかが意図しない結果になる。
また高架の是非が有権者の投票行動のすべてでないにしても、現状このことが沼津市政のリーダー選びに大きな要素となる。なぜならばこの問題がこれからのまちづくりや市民生活に大きな影響を与えるからだ。
4日の「語る会」を聴いたなかでは、このままの市長選では盛り上がらないのでないかと。何しろ具体的な施策ひとつも聴けなかったからだ。それはそうだろう。鉄道高架の是非を抜きにして沼津のビジョンや施策は語れない。
翻って、ついこの間行われた東京都知事選。当選した小池百合子知事はその選挙戦で、オリンピック施設の再検討、待機児童問題解消、行財政改革、韓国学校への都有地貸出取り止め、市場移転の点検、無電柱化、知事給与削減など、具体的な施策をいろいろと打ち出し、また議会との対決も辞さずと、その態度を鮮明に打ち出していた。その都知事選を目の当たりにすると、沼津市の市長選に寂しさを感じる。
候補者の人たちへ望みたい。鉄道高架問題の現実をスルーしては、沼津の将来が見えない。それ故、その是非のうえにたって、まちのビジョンを描き、その具体的な施策を示し、堂々と論戦を張っていただきたい。

2016年08月15日
終戦記念日に寄せて
8月15日。今年もこの日がやってきた。この日生まれた私は、誕生日といってもこの日に祝うことがなく (父母の意向で)、鎮魂の日として静かに過ごしてきた。生まれてからずっと、それは私の宿命と思い。
71年前のこの日の伊豆大仁。眩しいぐらいの青空の下、真夏の暑さと蝉しぐれの疎開先の家で、母は生まれたばかりの子を抱き寄せ、ラジオから流れる玉音放送を聞いた。子の行く末に思いを馳せ。(母の話)
それから幾千秋。その子は戦後社会とともに生き、この歳を数えた。そして日本は復興し、平和な国として戦後歩んできた。これからもずっと平和な国であってほしい。
しかし、よく考えてみると、日本は、戦後体制のままでないかと気づく。憲法ひとつとってみてもそうだ。今日まで一度も変えることがない。果たしてこれでいいのだろうか。当時と今では、世界情勢が大きく変わった。また変わったのは世界情勢だけでなく、日本人の国家観、歴史観なども変わってきた。一言でいえば、第二次世界大戦後すぐの戦勝国のあてがえ扶持のような統治体制に、現実は齟齬をきたしてきたといえる。
今まで続いた日本の繁栄と平和は、これからも続くという保証はない。また憲法9条があれば、他国が攻めてくることはないと信じている人がいるが、憲法9条が守ってくれることはない。現に中国の南シナ海、東シナ海などにみられる覇権主義的行動や軍事大国化、北朝鮮の拉致、核ミサイルなど、周辺諸国のこれらの動きを見ただけで、憲法9条が国を守ってくれるなどあり得ないことである。
外交は話し合いが基本である。その通りである。そして信じたい。しかし竹島や尖閣などの問題をみても、相手国は論理的な根拠がないから、話し合いのテーブルさえもついてこない。ただ日本が振り回されている現状である。足元の弱さにもつけ込まれて。
私たちは、これまでの繁栄と平和を次の世代へ繋いでいかなくてはならない。それは戦中戦後の日本を生きてきた人たち(父母)へ報いることである。その責務が戦後世代の私たちにある。そのためにも戦後の日本の歩みを踏まえ、現実の世界情勢、そして、しっかりとした国家観、歴史観、道徳観をもったうえで、平和国家のあるべき姿を描いていかなければならない。その正念場にきていることを国民一人一人が自覚する必要があると思う。平和な世界を祈って。

71年前のこの日の伊豆大仁。眩しいぐらいの青空の下、真夏の暑さと蝉しぐれの疎開先の家で、母は生まれたばかりの子を抱き寄せ、ラジオから流れる玉音放送を聞いた。子の行く末に思いを馳せ。(母の話)
それから幾千秋。その子は戦後社会とともに生き、この歳を数えた。そして日本は復興し、平和な国として戦後歩んできた。これからもずっと平和な国であってほしい。
しかし、よく考えてみると、日本は、戦後体制のままでないかと気づく。憲法ひとつとってみてもそうだ。今日まで一度も変えることがない。果たしてこれでいいのだろうか。当時と今では、世界情勢が大きく変わった。また変わったのは世界情勢だけでなく、日本人の国家観、歴史観なども変わってきた。一言でいえば、第二次世界大戦後すぐの戦勝国のあてがえ扶持のような統治体制に、現実は齟齬をきたしてきたといえる。
今まで続いた日本の繁栄と平和は、これからも続くという保証はない。また憲法9条があれば、他国が攻めてくることはないと信じている人がいるが、憲法9条が守ってくれることはない。現に中国の南シナ海、東シナ海などにみられる覇権主義的行動や軍事大国化、北朝鮮の拉致、核ミサイルなど、周辺諸国のこれらの動きを見ただけで、憲法9条が国を守ってくれるなどあり得ないことである。
外交は話し合いが基本である。その通りである。そして信じたい。しかし竹島や尖閣などの問題をみても、相手国は論理的な根拠がないから、話し合いのテーブルさえもついてこない。ただ日本が振り回されている現状である。足元の弱さにもつけ込まれて。
私たちは、これまでの繁栄と平和を次の世代へ繋いでいかなくてはならない。それは戦中戦後の日本を生きてきた人たち(父母)へ報いることである。その責務が戦後世代の私たちにある。そのためにも戦後の日本の歩みを踏まえ、現実の世界情勢、そして、しっかりとした国家観、歴史観、道徳観をもったうえで、平和国家のあるべき姿を描いていかなければならない。その正念場にきていることを国民一人一人が自覚する必要があると思う。平和な世界を祈って。