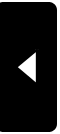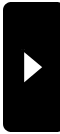2012年02月08日
アオキの赤い実
香貫山の登山道脇にあるアオキの木には、赤い実が一杯ついています。晩秋からの青い実が徐々に色づき真っ赤になりました。アオキは一年中、青々とした葉を茂らせていることからこの名前になったようです。アオキの花言葉は「若く美しく」とあります。誰でもいつまでも「そうありたいと」と思うことです。香貫山では、今、花の少ない季節ですので、アオキの赤い実がひと際目立ちます。


2011年12月26日
オニノゲシの花
香貫山の山頂付近の登山道脇で見つけたオニノゲシの花です。花はタンポポのような感じです。葉はギザギザでさわると痛いです。「鬼」とはどうしてついたのかわかりませんが、葉のギザギザに関係するのでしょうか。キク科ノゲシ属です。花言葉は「毒舌」「威厳」などとあります。


2011年12月25日
香貫山からの沼津のまち
ここ数日、寒い日が続きます。香貫山香陵台の五重塔です。この五重塔の後ろに富士山が見えるのですが、写真の時は雲がかかってしまいました。

香貫山香陵台からの沼津のまちです。まちの中を流れる狩野川。青く輝く駿河湾。千本松原、そして富士のまち。遠くには南アルプスの山々です。


香貫山香陵台からの沼津のまちです。まちの中を流れる狩野川。青く輝く駿河湾。千本松原、そして富士のまち。遠くには南アルプスの山々です。

2011年12月11日
枯れ葉と水仙と富士山
香貫山は、すっかり冬の装いになりました。ツワブキの花もほとんど終わって、登山道の両側は枯れ葉のたまり場になっています。

花が少なくなった香貫山では香陵台に水仙の花が元気よく咲いています。登山に来られる人に優しく微笑んでいます。

そして、これからの季節は富士山がとても綺麗に見えます。駿河湾の海とともに、その景色を楽しみに来て下さい。


花が少なくなった香貫山では香陵台に水仙の花が元気よく咲いています。登山に来られる人に優しく微笑んでいます。

そして、これからの季節は富士山がとても綺麗に見えます。駿河湾の海とともに、その景色を楽しみに来て下さい。

2011年12月07日
2011年12月04日
ムラサキシキブの実
香貫山桜台辺りの登山道脇のムラサキシキブの木には紫色の実がついています。庭などに植えられるムラサキシキブと呼ばれるコムラサキに比べて実のつき方がまばらで素朴な感じがします。ムラサキシキブの花言葉は「愛され上手」「上品」「聡明」となっています。


2011年11月18日
リュウノウギク(竜脳菊)の花
菊は似たような花がいろいろあって見分けに苦労します。プログにもユウガキク、ノコンギク、カントウヨメナなどいくつか掲載しました。今日のリュウノウギクも見分けが難しいのですが、葉が3裂していることからそうだろうとアップします。香貫山の登山道脇の斜面の日当りの良いところに咲いています。キク科キク属の多年草です。野菊の一種です。竜脳とはフタバガキ科のリュウノウジュの樹脂から取ってつくる香料で、その香りに似ているということでついた名前だそうです。花言葉は「無常の美」とあります。


2011年11月17日
ノイバラの赤い実
香貫山の登山道を歩いていると赤い実が目に入ります。ノイバラの実です。6月のときにハート型の花びらを5枚つけて咲いていた花の実です。花は清楚の中に強さを感じる雰囲気がありました。ノイバラの花言葉は「素朴な愛」「孤独」「才能」などとあります。またノイバラの実の花言葉として「無意識の美」というものもあります。

6月に咲いていたノイバラの花です。


6月に咲いていたノイバラの花です。

2011年11月16日
カタバミの花
香貫山の登山道脇の草むらに黄色のカタバミの花が咲いています。カタバミ科カタバミ属の多年草です。どこにでも見られる花ですが、ハート型の3枚の葉に囲まれた黄色の花が目立ちます。花言葉は「輝く心」です。


2011年11月15日
ダンドボロギクの花
香貫山の登山道脇の斜面にダンドボロギクの花が咲いています。北米原産の帰化植物で、一年草です。ダンドボロギクとは面白い名前ですが、この植物の発見地である愛知県の段戸山(ダンド山)に因んでつけられたそうです。それにしてもボロギクとはちょっと可哀想な気がします。花言葉は「強いこころ」ということで「ボロ」でも「めげない」気持ちがその花言葉に感じられます。考え過ぎでしょうか。


2011年11月12日
ユウガキクの花
香貫山の登山道脇の日当りの良い乾いたところに咲いています。カントウヨメナとそっくりですが、カントウヨメナは湿ったところに咲いていますので、この花は乾いたところですのでユウガキクかと思います。キク科ヨメナ属になります。花の名の由来は柚子の香りがする菊ということでユウガキク(柚香菊)というようになったそうです。近寄ったときには柚子の香りは感じなかったですが。。。


2011年11月10日
オオジシバリの花
キク科の植物です。香貫山の登山道脇草むらの比較的日当りの良いところに咲いていました。ヘラのような葉のかたちなどからオオジシバリの花に見えますが、調べるとこの花の花期は5~6月となっていますので、果たしてどうなのでしょうか。ちょっと疑問を感じながらもオオジシバリの花でないと否定することも出来ないのでこのままアップします。


2011年11月08日
2011年11月07日
カントウヨメナの花
香貫山の登山道脇にカントウヨメナが咲いています。キク科ヨメナ属です。すらっと伸びた花びらがとても綺麗です。葉には少しだけギザギザがあります。花の名の由来は、美しい姿を嫁にたとえたことからだそうです。ヨメナという名前からも初々しい花嫁の姿をイメージします。ユウガキクとも似ていますが、やや湿ったところに咲いていましたのでカントウヨメナとして掲載します。花言葉は「隠れた美しさ」です。


2011年11月05日
コウヤボウキの花
コウヤボウキの花です。香貫山の日当りの良い登山道脇の草むらに咲いています。キク科コウヤボウキ属の落葉小低木です。花は1年目の茎に一輪ずつ咲き、花びらは細長くよじれています。花の名前の由来は、高野山で茎を束ねて箒の材料としたことからついたようです。花言葉は「清潔」「働き者」とあります。ふたつの花言葉から結びつくものは「箒で綺麗にするために一生懸命に働く人」となりますが。。。


2011年11月03日
ヨウシュヤマゴボウの実
香貫山の登山道を歩いていると、ちょっとぶどうのように見える実が目に入ります。ヨウシュヤマゴボウの実です。ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属です。多年草で北アメリカ原産の植物です。日本では明治初期以降に入ってきたようです。夏に果実をつけ秋に黒く熟します。名前の由来は根が太く、その姿がゴボウに似ているからだそうです。花言葉は「野生」「元気」「内縁の妻」とありました。ヨウシュヤマゴボウは有毒植物です。間違って食べないようにしてください。


2011年11月02日
ノハラアザミの花
香貫山の登山道脇の草むらにノハラアザミ(野原薊)の花が咲いています。キク科アザミ属です。春に咲くのはノアザミ(野薊)です。ノハラアザミの特徴は葉に深い切り込みがあり葉や総苞にトゲが多いことです。先日、タムラソウの花を掲載しましたがノハラアザミの花にそっくりです。キク科は同じですがタムラソウ属です。ノハラアザミの花言葉は「心の成長」です。


2011年10月31日
コセンダングサの花
香貫山の登山道脇の乾燥したところに黄色いチリチリの花が咲いています。コセンダングサの花です。キク科の一年草です。熱帯アメリカ原産の帰化植物です。チリチリの花とギザギザの鋸歯の葉が特徴的です。コセンダングサは道路沿いや荒地に生えていますが、ほっとくとどんどん増えていきます。そういった意味では困った植物です。花言葉は「味わい深い」です。


2011年10月30日
ヤマハッカの花
香貫山の香陵台から北側を行くルートの登山道脇斜面に小さな紫色の花が咲いています。シソ科のヤマハッカです。何段にも薄紫色の小さな花が数個ずつかたまって咲いています。綺麗な花です。花言葉は「思いやり」です。たしかに優しそうな感じがします。